2016年12月21日
ムジカノーヴァ連載開始 『表現のコツ』
ムジカノーヴァ1月号から、
『表現のコツ〜自分が求めている音楽を奏でるために〜』を
連載することになりました。
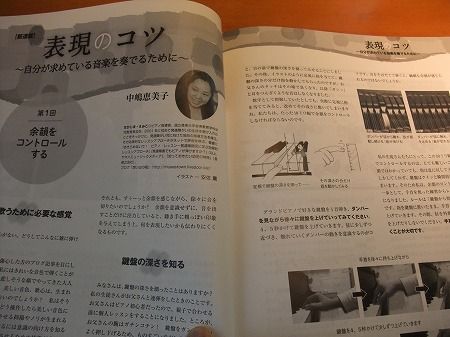
第1回のテーマは ≪余韻をコントロールする≫ です。
楽器の特性を知り、
その可能性を耳や指で感じ取る力を養うことは、
表現する上でとても大切なことではないでしょうか。
先日、中学3年生の女の子に、
最終音のペダリングについてレッスンしました。
曲は、轟千尋さんの『雨上がりの朝』です。

『表現のコツ〜自分が求めている音楽を奏でるために〜』を
連載することになりました。
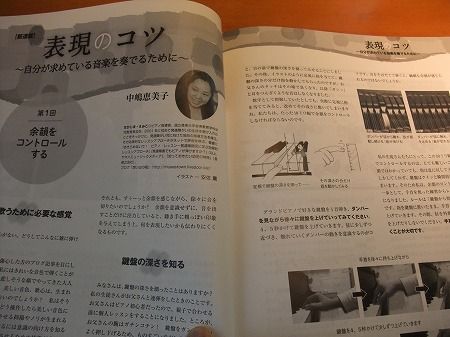
第1回のテーマは ≪余韻をコントロールする≫ です。
楽器の特性を知り、
その可能性を耳や指で感じ取る力を養うことは、
表現する上でとても大切なことではないでしょうか。
先日、中学3年生の女の子に、
最終音のペダリングについてレッスンしました。
曲は、轟千尋さんの『雨上がりの朝』です。

轟 千尋
全音楽譜出版社
2016-06-14
ソナタアルバムを弾いている子なので、
この子にとってはかなり易しい曲集なのですが、
対位法が多く使われている上、
バロックや古典派にはない、
ロマン派・近現代的な響きが豊富に扱われているので、
とてもいい経験になります。
「この曲を作った作曲家の轟千尋さんは、
ものすご〜くアーティキュレーションにこだわりがあったんだと思うなぁ。
ここは、どうしてこういうアーティキュレーションにしたのかな?」
アーティキュレーションの語尾は、
どういう余韻がこの曲のイメージに合うのか?
ペダリングはどうしたらよいのか?
楽器の特性や可能性を知らなければ、
表現しきれない繊細な曲。
生徒さんはこの曲が大好きで、
イメージは存分な広がりと奥行きを持っているのですが、
それを実際にピアノで表現するとなると、
これがなかなか。(笑)
楽器の特性や可能性がわかったところで、
今度は自分の耳を頼りに、
体をコントロールできなければならないのですから、
当然ですよね。
表現を抜きにすれば、
とりあえず楽譜通りに指は動く。
そういう意味でのテクニックはさほど難しくない。
音数も多くない。
こういう一見易しそうに見える曲で、
音楽表現の奥行きを学べるというのは、
本当にありがたいこと。
ロマン派以降の曲は難しい曲が多いですから、
なおさらこの曲集は貴重です。
話が少し逸れてしまいましたが、
この曲の最終音のペダリング。
何度試しても、
なかなか本人の納得がいくような余韻になりません。
そこで、譜面台をピアノから取り外し、
1月号の連載記事に書いたように、
ダンパーの動きを見ながら、
ペダルの実験をしてもらうことにしました。
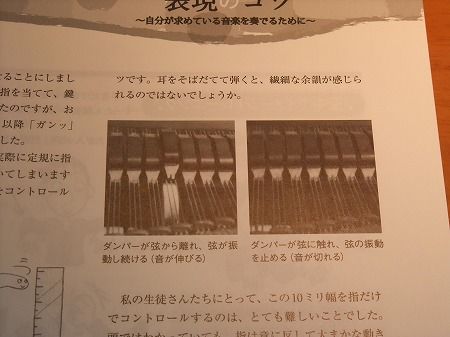
難しいのは、ダンパーと弦が、
触れるか触れないかという距離からの、
ペダルのコントロールです。
踏み込んだ足を半分上げる程度までは、
それほど難しくないんですよね。
問題はそこから。
ダンパーを覗き込みながら、
あれこれ試す生徒さんの横顔を見ると、
目をきらきらと輝かせて、
ペダルの実験にのめり込んでいるのがよくわかります。
私はこういう瞬間が大好き!
先生に言われたから・・・ではなく、
自分がそういう表現を求めているからこその目の輝き。
この連載では、この曲はこう弾くべき、
こう解釈して、こう弾かなければならない、
という視点で語るのではなく、
楽譜の読み込みから得たイメージを
ピアノで表現するにはどうしたらよいのか?
という視点を大切に書いていきたいと思っています。
ピアノの練習や表現が、
苦役ではなく、喜びとなりますように。
クリックで応援してネ♪
emksan at 15:52│TrackBack(0)│
│ピアノ/レッスン


